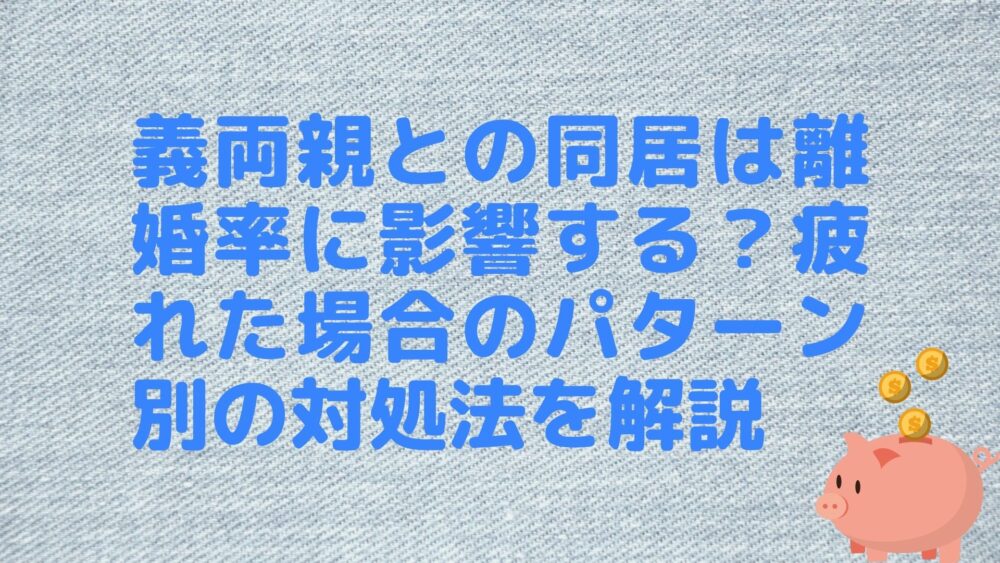「義両親との同居」というと、あなたはどのような印象を受けますか?
小言、干渉、口出しなどネガティブな言葉ばかりが浮かぶのではないでしょうか。
テレビドラマや映画であればハッピーエンドになりますが、現実ではほぼバッドエンドが待っています。
筆者は男で、結婚してマスオさん状態(妻の実家に婿入りをせず同居)の10年目で離婚をしました。
弁護士の先生にもお願いをしました。
あなたには筆者のようになってほしくありません。
- 同居を迫られている
- 同居が決まってしまった
- 同居が始まった
- 同居に疲れた
- 離婚したい
あなたの状況が上記に当てはまるのなら、この記事は必見です。パターン別の対処法や離婚率に影響するのか?という観点でも解説しているので、ぜひ最後まで目を通して自分を守り抜いてください。
義両親との同居は離婚率が上がる?
冒頭にも書きましたが、やはり義両親との同居は離婚に直結するイメージが強く、できれば避けたいものです。
では、義両親との同居と離婚率の関係性を見ていきましょう。
そもそも「離婚率」は「離婚する確率」ではない
まずは下記のグラフをご覧ください。
出典:厚生労働省 令和5年(2023) 人口動態統計月報年計(概数)の概況
このグラフは、昭和22年から令和5年までの離婚件数と離婚率の推移を表したものです。
令和5年の離婚率は1.52になっています。
この数値は、100組中1.52組が離婚するという確率(パーセンテージ)ではなく、人口1,000人あたり1.52組が離婚しているという意味になります。
離婚率とは、人口1,000人あたりの離婚件数を意味します。
そもそも義両親との同居義務はない
夫婦は、民法752条に「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」と定められており、同居の義務が発生します。
しかし、義両親との同居は明文化されておらず、たとえ断っても法的には何の問題もありません。
もっと言えば介護の必要もありません。
出典:民法877条 e-Gov 法令検索
上記のように定められており、嫁や婿は扶養義務者でないことがわかります。
「長男の嫁は介護をするのが当たり前」なんて時代は、とっくの昔に終わっています。
義両親との同居はしないに越したことはない
20〜30代の男女200人へのアンケートで次のような結果が出ています。
出典:共有持分の教科書
義両親との同居は悪いイメージが先行しているのもあるかもしれませんが、やはりあらゆる問題が降りかかってくることは紛れもない事実です。
想定外のことが起こることも少なくありません。
現在同居が決定していないのであれば、まだ間に合います。
「義両親との同居はしません!」と訴えてください。
絶対に負けないでください。
義両親との同居を避けられないのなら
配偶者は「経済的に助かるから」「親がかわいそう」などのキラーワードで訴えかけてくるでしょう。
情に流され、義両親との同居を受け入れてしまったあなたは優しい人です。
同居生活のストレスが少しでも減るよう、きちんと対策をしていきましょう。
同居前にやること
同居前にやっておくとよいことを見ていきます。
同居の認識を夫婦ですり合わせる
当たり前ですが、あなたの義両親は配偶者から見れば実の親です。
そのため、配偶者は「うちの親はきちんとしている」「話せば何でもわかってくれる」などと、過大評価していることがよくあります。
また、親に全く関心がなく同居の難しさを全く理解していないケースもあります。
いずれにしても、配偶者は自分が家庭においてクッションの役割を担っていることを自覚していません。
この点を夫婦でしっかりと話し合っておく必要があります。
同居のルールを決めておく
義両親も含めた家族全員でルールを決めます。
同居において忘れてはならないのは、「暗黙のルール」は通用しないということです。
生活する上で気になる点を以下にあげてみます。
- 冷蔵庫の使い方
- 風呂や洗面所を使う時間帯
- 洗濯物の干し方
- ゴミの分別
- 郵便物の処理方法
- 光熱費や住宅ローンなどの金銭面
- 子供の食物アレルギー
家庭ごとに生活環境が異なるため細かくあげていけばキリがありませんが、じっくりと考えておきましょう。
ある程度ルールが決まったら、しっかりと文面に残して全員が共通認識を持てるようにしたいものです。
また、子供の成長などに合わせて定期的にルールを見直し、ガチガチではなく柔軟に対応していくことが大切です。
義両親との生活スペースを分けておく
個人スペースと共有スペースをしっかりと分けるようにしましょう。
1,000名以上のママへの帰省に関してのアンケートで次のようなものがあります。
出典:Mapion
これは同居ではなく「夫の実家への帰省で何泊しますか?」という内容ですが、圧倒的に多いのが「帰省しない」という回答です。
同居ならまだしも帰省でこの結果です。
たった数日であっても義両親に会うことすら拒否したいということは、同居がいかにストレスが多いのかを物語っています。
やはり、同居であっても「自分だけのスペースを持つ」ことが重要です。
逆を言えば自分がされたくないことは人にもしない、要は義両親に対して深く踏み込まないことが鉄則です。
義両親の評判をご近所にたずねる
人間には家族に見せない顔というものが少なからずあります。
その顔がよい顔であるならば何の問題もありませんが、そうでない場合もあります。
そこで、ご近所への挨拶の時にそれとなくたずねてみましょう。
「立派なおうちにお嫁にこられてよかったね」
「ご両親には本当にお世話になってるの」
「立派なご両親よね」
上記のように、たとえ冗談まじりであっても、義両親をベタ褒めしすぎている場合は注意が必要です。筆者の主観ですが、ご近所の方々が義両親の顔色をうかがっている可能性があります。これは、義両親に裏の顔が潜んでいる証拠なのかもしれません。
同居が始まったら
では、いよいよ同居が始まります。
配偶者に協力してもらう
義両親との同居は、配偶者の協力が不可欠です。
なぜなら、同居の「言い出しっぺ」はほとんどの場合において配偶者だからです。
下記のグラフをご覧ください。
まず「夫が長男」というだけで、妻の幸福度が下がっています。
次に「義両親と同居」の幸福度の低下幅は「夫が長男」に比べて、2.4倍に跳ね上がっています。
先ほど「同居の言い出しっぺは配偶者」と書きましたが、長男は責任感の強さゆえに同居を提案することが多いようです。
言い出しっぺには家庭においての「クッション」はもちろん、「潤滑油」の役割も担ってもらうしかありません。
いや、一番よいのはお互いの悪い面が見えないように「フィルター」になってもらうことかもしれません。
あえて義両親とコミュニケーションをとる
配偶者以上に義両親と仲良くなるのもよい方法です。
- 一緒に買い物に行く
- 共通の趣味を持つ
- プレゼントをする
- 感謝の言葉を絶やさない
- 子供(孫)に一役買ってもらう
上記などに配偶者の知らない情報をちょっと散りばめるのがコツです。
例えば、買い物の際に配偶者には内緒で美味しいと話題のお店に行くなどの「秘密の共有」を意識すると、今後に繋がっていくでしょう。
この方法は、聞き役に徹して出しゃばらず、それでも過度な遠慮はしないというような、絶妙な立ち位置が求められるため、上級者向けと言えるかもしれません。
慣れてくると、義両親と一緒になって配偶者の愚痴を言えるようになります。
義両親と会う機会を減らしてみる
義両親とコミュニケーションを取るのが苦手な場合は、思い切って会う機会を減らしてみましょう。
ただし、単なる外出だと顔を合わせないようにしているのがバレてしまい、下手をすると配偶者に告げ口をされてしまいます。
そうならないためにも、パートやアルバイトなどの仕事をしてしまえば、外出の理由ができます。
シフト制の仕事であれば出勤時間や退勤時間がその都度変わるため、うまくいけば食事などの時間をずらすことができるかもしれません。
地域の寄り合いなどへ積極的に参加する
義両親が地域の寄り合いに参加しているのであれば、あなたが代わってあげましょう。
義両親へ「お疲れでしょうから」などと声をかけておけば、代わってくれたと喜ばれるでしょうし、参加するとご近所から有利な情報が得られるかもしれません。
主導権を静かに奪ってしまいましょう。
あくまでも「静かに」です。
義両親との同居に疲れたら
いろんな方法を試したけど、やっぱり義両親とは合わず疲れてしまったら、どうすればよいのでしょうか。
同居を解消する
ここまで頑張ったからなどと考えずに、思い切って配偶者に同居の解消を提案してみましょう。
あなたがいかに追い詰められているかを、プレゼンをするように説明していきます。
この時に注意することは、同居の解消理由を義両親ではなくあなた自身にすることです。
なるべく義両親を悪者にしないようにすれば、配偶者は同居の解消に協力してくれるかもしれません。
もし、いくら説明をしても「子供が懐いてる」「気にかけてくれている」などのキラーワードで訴えてくるようなら、下記のようなキラーワードで対抗しましょう。
ポストURL:https://x.com/Jv9nSu2VGNVWBAK/status/1655894772593348608
離婚を考える
離婚は最終手段ではありますが、どうしても状況が変わらない場合は、選択肢の一つとして考えてもいいかもしれません。
子供がいると迷いもあるかもしれませんが、親が心身ともに健康であることが何より大切です。まずは他の方法を試してみて、それでも難しければ、冷静に次の一歩を検討してみましょう。
同居のストレスを離婚理由にできる?
義両親との同居を離婚理由にできるのでしょうか。
下記のグラフをご覧ください。
これは、離婚調停の動機を申立人数別に表したものです。
中央より少し下に「家族親族と折り合いが悪い」という項目があります。
また、下から2番目に「同居に応じない」もあるため、直接配偶者に関することでなくても離婚理由になることがわかります。
配偶者の同意があれば離婚はできる
離婚は配偶者の同意があれば成立します。
配偶者の同意さえあればよいので、必ずしも離婚理由が必要とは限りません。
しかし、簡単に配偶者の同意が得られるのなら、前述した離婚調停申立人のグラフは存在しないはずです。やはり、配偶者も離婚を突きつけられて「はい、よろこんで」とはならないのです。
配偶者が離婚に同意しないときは
では、配偶者が離婚に同意しないときはどうすればよいのでしょうか。
一時的に実家に帰る
実家に帰って気持ちを落ち着かせましょう。
配偶者の実家は常にアウェイ感があり、離婚の話し合いには不向きです。
実家ならあなたの両親や親族に相談することができ、今後の作戦を立てられます。
ドラマなどでは、配偶者が帰宅したら荷物をまとめて出て行ってたなんてシーンがよくありますが、現実では配偶者に実家に帰ることを伝えた方がよいでしょう。
もし裁判になった場合、感情的な行動は不利になる可能性があります。
あくまでも事務的に事を進めていきましょう。
帰る理由は「いろんなことを考えすぎて体調が悪い」「一度、頭を冷やしたい」など、やはり自分自身を理由にすると成功率が上がります。
弁護士に相談する
次のようなケースの場合は弁護士に相談をしてみましょう。
- 配偶者が話を聞かない
- 義両親に告げ口をされた
- 子供がいると話ができない
- 実家に帰るとご近所の噂になる
しかし、やはり弁護士は敷居が高いイメージがあります。
「こんなことで相談していいの?」と思うかもしれませんが、親身になって話を聞いてくれます。
下記のグラフをご覧ください。
出典:①PR TIMES ②法律相談プラットホーム「カケコム」
上記のグラフを見て、あなたは「はい」の割合が多いと思いますか?
筆者はまだまだ少ないと感じました。
義両親との同居という問題は、こじらせると厄介になります。
離婚に発展してしまう前に、なるべく早く弁護士へ相談をすることをおすすめします。
では、「はい」と答えた54名へのアンケート結果も見てみましょう。
出典:①PR TIMES ②法律相談プラットホーム「カケコム」
弁護士に相談をした方のうち、およそ9割が「相談してよかった」と感じています。
もしかすると、依頼するまでもなく相談だけで問題が解決してしまうかもしれません。
まとめ
今回は義両親との同居と離婚の関係、また同居に疲れた場合の対処法をご紹介しました。
家族だと思っていた人が急に敵対することが現実にはあります。あなたにはそんな悲しい思いをしてほしくありません。
義両親との同居に不安がある場合は、無理に受け入れず、自分の心に正直に向き合うことが大切です。そして、少しでも違和感やストレスを感じたら、早めに相談することをおすすめします。
弁護士は最後の砦ではありますが、相談することで新たな視点が得られることもあります。
こちらの記事もおすすめ:夫婦のお金の管理どうしてる?揉めないために新婚の時に取り組むべきこと
ライター名:千羽隆二(せんばりゅうじ)